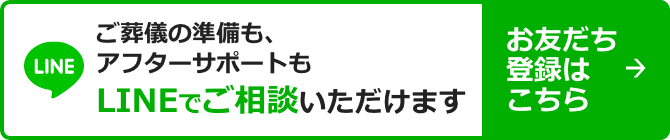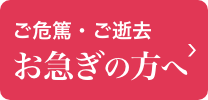お葬式の豆知識
法要のお供え物マナー|包み方・渡し方・郵送方法

法要にお供え物を準備する際は、金額や品物の選び方だけでなく、包み方や渡し方にも配慮が必要です。掛け紙の種類や表書き、水引の色などは、法要の時期や宗派によって適切なものが異なります。
また、お供え物を渡すタイミングや施主への挨拶の仕方も大切なマナーのひとつです。さらに、やむを得ず欠席する場合には、郵送によって弔意を示す方法もあります。本記事では、法要のお供え物に関する包み方・渡し方・郵送の基本マナーを解説します。
法要のお供え物、包み方マナー
◇法要にお供え物を持参する場合は「外のし」
一般的に、のし紙と呼ばれますが、本来は弔事の場合「掛け紙」とされます。百貨店などでは水引まで印刷された、弔事用・慶事用ののし紙があるでしょう。また、のし紙には包装紙の下にかける「内のし」と、包装紙の上にかける「外のし」という2種類があります。
<法要のお供え物:のし紙>
①内のし…お供え物を郵送する際に利用
②外のし…お供え物を持参する際に利用
外のしの場合、誰からのお供え物かが一目で分かり、持参する時に便利です。郵送では伝票に名前が記載されているため、必ずしも外のしである必要はありません。
①表書き
◇一般的な表書きは「御供」
水引の下には、贈る人の氏名を記入しましょう。法要のお供え物で、先方の宗派が分からない場合、基本的な表書きは「御供」「粗供養」であれば、失礼にはなりません。
このほか、「御霊前」「御仏前」などの表書きもありますが、この場合は、四十九日前の忌中に執り行う法要のお供え物であれば「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」と使い分けます。ただし、浄土真宗による法要であれば、四十九日前でも「御仏前」になるため確認が必要です。
②水引
◇のし紙は、白黒の水引が印刷されたものを選ぶ
一般的に法要のお供え物をお店で注文すると、水引まで印刷されたのし紙(掛け紙)が掛けられるでしょう。そうでなければ、四十九日までの忌中は、白黒の水引を選びます。さらに四十九日以降の忌明けになると、双銀の水引、三回忌以降は黄白の水引に変わる地域が多いです。ただし、地域性もあるので、親族や周囲に確認をしながら準備をしましょう。
法要のお供え物を渡すタイミングは?
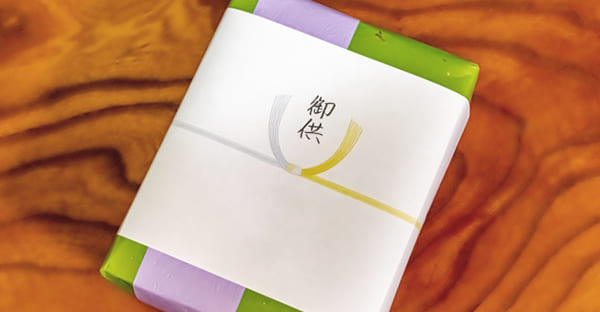
◇法要のお供え物は、施主へのご挨拶とともに渡す
法要に香典とお供え物を持参する場合には、香典とお供え物を揃えてお渡ししながら、「御仏前にお供えください」など一言添えると丁寧です。施主以外の方に渡したり、勝手に仏壇に供えたりするのはマナー違反になるため、注意しましょう。特に大人数の法要では、誰からのお供え物かが混乱しないよう、渡す際の言葉や掛け紙の表記が重要な役割を果たします。
法要のお供え物の渡し方
◇法要のお供え物は、紙袋に入れて持参
法要でお供え物は紙袋に入れて持参し、渡す際には、紙袋からお供え物だけを出し、中身を施主に渡すのがマナーです。紙袋は無地の濃紺や茶色、グレーなどの落ち着いた色柄で整え、紙袋がない場合は、風呂敷に包むこともできます。風呂敷の場合も、紙袋と同じく中身だけを渡し、いずれも持ち帰りましょう。
こうした細やかな所作は、ご遺族に対する思いやりが表れる部分です。形式を守ることが、相手に余計な気遣いをさせない心配りにつながります。
法要のお供え物は送ってもいい
◇法要のお供え物は郵送しても失礼にあたらない
法要に参列できない場合に、お供え物を郵送すると丁寧です。法要のご案内が届いたら、できるだけ早い段階で欠席の連絡をしましょう。この時、法要にお供え物を郵送する場合には、施主に前もって連絡しておき、法要までにお供え物が届くように手配します。また法要のお供え物には、挨拶状や手紙などを添えて郵送すると丁寧です。
例えば「このたびは法要に伺えず申し訳ございません。心ばかりではございますが、お供えの品をお送りいたします。ご仏前にお供えいただければ幸いです」といった一筆を添えると、形式だけでない誠意が伝わります。
まとめ

法要のお供え物は、心を込めて準備することが何より大切ですが、その気持ちを正しく伝えるためにはマナーの理解が欠かせません。包み方では掛け紙や表書き、水引を場面に応じて使い分け、渡す際は施主への挨拶とともに丁寧に手渡しましょう。
紙袋や風呂敷の扱い方も含め、細やかな気配りが必要です。また、参列できない場合には郵送で弔意を示すことも可能で、その際は挨拶状を添えるとより丁寧です。こうした基本を押さえることで、失礼のない、心のこもった供養が実現します。
マナーは形だけのものではなく、ご遺族に余計な負担や気遣いをさせないための配慮です。大切なのは**「相手を思う心」**であり、その心を伝える手段としてマナーが存在します。形式を整えつつ、温かい気持ちを添えたお供え物を準備することこそが、真の供養につながるでしょう。