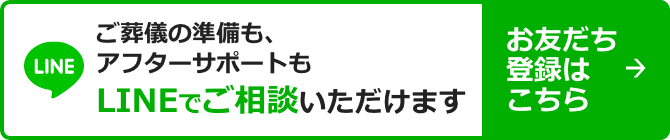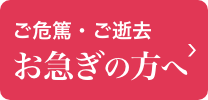お葬式の豆知識
沖縄で行う火葬とは?火葬場での流れを解説

火葬とは、ご遺体を焼却してご遺骨の形にする葬送のひとつです。現代の日本では、ほとんどの墓地で火葬しなければ埋葬ができません。そのため葬儀の後にほぼ火葬を行いますが、沖縄では最初に身内のみで火葬を済ませ、ご遺骨の状態で葬儀・告別式を行う「骨葬(こつそう)」が一般的です。
今回は、沖縄の葬儀における火葬について、火葬場での流れやそれぞれの意味をお伝えします。
火葬とは?骨葬(こつそう)とは?
●火葬とはご遺体を焼却して埋葬する葬送方法
火葬とは、ご遺体を焼却してご遺骨にしてから埋葬する葬送方法のことです。その昔の日本では、ご遺体を土に埋葬する「土葬」、特に沖縄では遺体の風化を待つ「風葬」がありましたが、現代では各地域の条例などによって火葬場で火葬して、ご遺骨の状態にしてからお墓に埋葬、納骨堂や手元供養などの形で葬送しなければなりません。
●ご遺体を焼却して遺骨の形にしてから葬儀する骨葬
沖縄では、通夜を身内だけで行い、ご遺体を火葬してからご遺骨の状態で葬儀を行う骨葬という葬送方法が一般的です。沖縄では独特の気候によって、ご遺体の衛生状態もあまり長く維持できません。
火葬場での流れ
火葬場では①納めの式→②火葬→③骨あげ、と進みます。ご遺体を火葬場に運んだら、火葬炉の前にご遺体が安置され、祭壇の前には仮位牌(シルイフェー)と遺影が祀られて、納めの式が始まります。
「納めの式」はご遺族がご遺体を前にした最後の別れの儀式のことで、火葬前にお焼香をして、ご遺体のお顔と対面してお別れを言います。
<火葬場での流れ>
●納めの式
①ご遺体の安置 → ②お焼香 → ③故人と最期の対面
●火葬
④火葬 → ⑤骨上げ
●ケースによって
⑥還骨法要 → ⑦お斎
沖縄では、たとえ葬儀や告別式の後で火葬を行う場合でも、一般参列者は葬儀・告別式までとし、火葬場は身内のみが行くというのが一般的です。また、沖縄は特定の仏教宗派を信仰する檀家(だんか)は少ないですが、浄土真宗を信仰する家では、最後の骨上げは行われません。(浄土真宗では亡くなってすぐに成仏するため、橋渡しの必要がないという理由)
①ご遺体の安置
火葬場に運ばれたご遺体は火葬炉の前に安置され、小さな祭壇が整えられます。祭壇には、仮位牌であるシルイフェーと遺影が祀られ、同行した僧侶の読経供養を行う準備が進められますが、僧侶の同行がない場合、読経供養は省略されます。
②お焼香
祭壇の前で僧侶の読経供養が行われ、同行したご遺族がお焼香をします。お焼香の順番は沖縄の葬儀と同じです。故人と一番近しい喪主やご遺族から始まり、近親者、火葬場まで同行した故人と近しい一般会葬者へと続いてください。
③故人と最期の対面
棺の小窓を開けて、故人と最期の対面を行います。沖縄で通夜や葬儀を執り行うことなく、火葬場で全てを済ませる「直葬」や、沖縄で葬儀前に火葬を済ませる「骨葬」の場合、ここで「別れ花」の儀礼を行うこともあります。
「別れ花」とは、火葬場にいる喪主や遺族、参列者がひとりひとりユリなどの花を持ち、棺に納めながら別れを告げる儀礼のことです。
④火葬
火葬場の休憩室で、火葬が終わるのを待ちます。火葬の時間はおおよそ2時間~3時間ほどですので、喪主(施主)は同行しているご遺族や参列者の人々へ、お菓子などのお茶請けや軽食などを準備するのが一般的です。
火葬の待ち時間が昼食時間に重なるならば、仕出し弁当などの昼食を用意すると親切です。人数により異なりますが、仕出し弁当の目安としては500円~1000円/1人ほどになります。
※仕出し弁当は弔事用のものを注文してください。
⑤骨上げ
焼骨されたご遺骨を、左右に立つ2人1組でお箸で取り上げて骨壺に入れます。2人1組で行う理由は、故人を「橋(箸)であの世へ渡す」という意味を持っています。そのため、亡くなってすぐに成仏する浄土真宗では、橋渡しの必要がないことから、骨上げは行われません。
<骨上げの順番>
●故人と血縁関係の深い順番から
①喪主→②ご遺族→③近親者→④一般参列者
●ご遺骨を上げる順番
①足の骨→②腕の骨→③腰の骨→④肋骨→⑤歯→⑥のど仏→⑦頭
骨上げは、足元から順番に骨壺に納め、最後にのど仏を乗せた後、頭を被せて納めます。のど仏は「小さな仏様」などとも言われ、ご自宅で遺骨を手元供養したい時や分骨したい時に、喪主やご遺族は「のど仏」のみを分けてもらいます。
◇沖縄独特の骨上げ
一般的に骨上げは2人1組で行いますが、沖縄の骨上げでは故人と近しいご遺族3名で行う風習もあり、3人1組、横並びでお骨を受け渡し、3番目の方が壺の中へ納めます。
⑥還骨法要
ご遺骨になって自宅へ戻ってきた故人を供養する儀礼のことを「還骨法要」といいます。還骨法要では、後飾り祭壇に、火葬を終えた骨壺やシルイフェー(仮位牌)、遺影を祀り、僧侶に読経供養をお願いします。ただ、最近ではハチナンカ(初七日法要)と一緒に還骨法要を行う場合も多いでしょう。
⑦お斎
お斎(おとき)では、火葬の後に喪主(施主)が会食を参列者へ振る舞いますが、沖縄では、火葬後のお斎が省略されることや、お持ち帰りの仕出し弁当が用意されることも少なくありません。お斎(おとき)を執り行う場合には、喪主(施主)は下記の準備も必要となります。
<お斎(その他の準備)>
・僧侶の出欠席の確認(欠席の場合は「御膳料」の準備)
・お斎の席数(会場)
・喪主挨拶
会場は地域の集会所や人数によってはレストランなどの他、斎場のスペースを利用することもあります。また火葬後にそのまま納骨した場合、霊園の個別法要スペースを借りることもあるでしょう。
※高齢の参列者も予想されるため、火葬場から離れたお斎会場の場合には、交通手段の確保も配慮が必要です。
まとめ

沖縄の火葬や火葬場での流れについて解説してきましたがいかがだったでしょうか。基本的な流れは本土と一般的には変わりませんが、火葬をしてから葬儀を行う骨葬が一般的であったり、骨上げに係る人数などに違いがありました。
昔は風葬や土葬が一般的でしたが、葬送方法が変化してきた現代でも故人を弔うという気持ちは同じです。一般的な流れを知って落ち着いて葬儀に臨んで、故人と最期のお別れをしましょう。