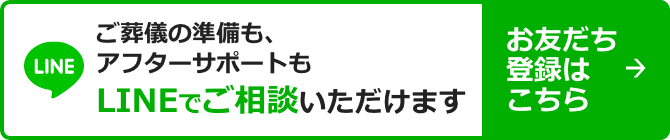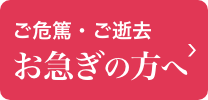お葬式の豆知識
沖縄の初盆(みーぼん)で必要な準備とは?弔問対応とお供えのマナーを解説

血縁関係のない友人や知人の危篤のお知らせを受けたら、会いに行くべきか控えるべきか……迷う人も少なくありません。本人の家族から危篤の知らせを受けたのなら、もちろんすぐに駆け付けても良いですが、家族への配慮は不可欠です。
今回は迷いやすい、危篤の知らせを受けた時の対応や判断基準を解説します。
ご家族から危篤の知らせを受けたら
●直接であればすぐに駆け付ける
危篤の知らせを受けた場合、誰から知らせがあったかによって対応は変わります。特にご家族から危篤の知らせを受けたなら、あなたは本人と近しい血縁関係者、もしくはごく親しい間柄、ではないでしょうか。
<危篤の知らせ>
①家族から直接
・病院と病室を確認し、すぐに駆け付ける
・服装はふだん着のまま
②間接的に
・自分の立場で判断する
危篤の知らせを受けた場合、少しでも早く本人に会いたい、元気になってほしい……そんな気持ちで駆け付けるため、服装はふだん着のままで大丈夫です。
ただし、本土や遠方から沖縄に駆け付ける場合は、そのまま通夜・葬儀(告別式)になる可能性も考慮して喪服や御香典の準備はしておきましょう。
ご臨終に立ち会う

●ご臨終に立ち会うことになってしまったら
危篤の知らせを受けて駆け付けたら、そのままご臨終に立ち会う場合もあるでしょう。血縁関係がないと「私がいても迷惑だから……」とおいとまするべきかと考えてしまうかもしれませんが、家族が危篤を知らせた限りはその場にいることは問題ないでしょう。ただし、立場をわきまえた対応は必要です。
<危篤の知らせ:ご臨終>
①尊重したい人
・配偶者
・同居家族(子どもなど)
・血縁は薄くとも、最も身近にいた人
・危篤までお世話をしてきた人
②配慮する人
・友人知人
・他家へ嫁いだ本人の娘
例えば、危篤者本人の娘であっても他家へ嫁いでいるのであれば、すでに他家の人間なので、最後まで本人のお世話をしてきた人々を押し退けて、ベッド脇で体にとりすがる行為などはわきまえましょう。
●ご臨終の時の所作
その場にいる誰にとっても本人との最期の時間であることを意識して対処しましょう。危篤の知らせと同じように訃報を受けた場合でも、服装はそのまま駆け付けるのがマナーです。
一般的な通夜と違い、沖縄では近親者のみで執り行う通夜を風習とすることが多いので、危篤の知らせだったものが訃報になってしまった場合、故人と血縁関係のない知人友人は「このまま行っても良いのだろうか?」と迷ってしまうかもしれません。しかし、危篤の知らせを家族から受けたのであれば、それだけ故人と近しい関係であることは家族も理解しています。
<危篤の知らせ:訃報>
①近親者や親族…そのまま駆け付ける
②友人や知人…特に親しい人は駆け付ける
└手伝いを申し出る
危篤の知らせを受けた後、ご臨終の後や通夜に着いたら、まずお悔やみの言葉を伝えてからお手伝いを申し出ましょう。最近では葬儀社スタッフが全てを担ってくれる葬儀(告別式)も増えましたが、通夜の席に参加する間柄であれば、翌日の葬儀(告別式)の世話役を買って出て、通夜ではその打ち合わせを行うと遺族も助かりますし、故人もきっと喜ぶことでしょう。
また、特に沖縄では、地域によっては危篤から葬儀までの時間が短く、準備が慌ただしく進むことも珍しくありません。遺族が精神的にも肉体的にも負担を抱えている中で、周囲の人が率先して動くことで、場が落ち着き、滞りなく進行できる場合があります。こうした配慮や行動は、形式的なマナー以上に、残された人々の心に深く感謝として残るものです。
まとめ

以上が危篤の知らせを受けた時、会いに行くべきかどうか……臨終に立ち会う場合の配慮、その後の流れでした。基本的には間接的に危篤の知らせを受けたり、本人と近しい関係性でなかったりするなら、できるだけ駆け付けるのは控えた方が無難でしょう。
その後に訃報を受けたなら、沖縄であれば翌日の訃報欄を確認して、葬儀(告別式)の参列のみに留めた方が適切です。その代わり、本人と特に親しい関係性だったり、家族から連絡を受けたなら、誠意を持って対応しましょう。
なお、危篤の知らせは突然入ることが多く、慌ててしまいがちです。日頃から弔事用の小物(数珠・香典袋・筆ペンなど)を一式まとめておくと、急な移動でも落ち着いて行動できます。また、病室では長居せず、短い言葉や表情で気持ちを伝えることが大切です。病状や場の雰囲気に応じて、必要以上に話しかけず、静かに寄り添う姿勢が望ましいでしょう。