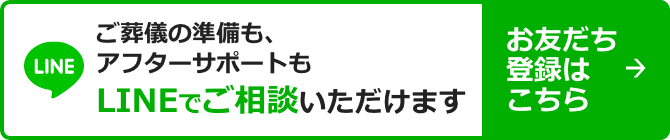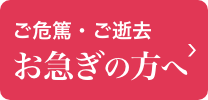お葬式の豆知識
【清明祭】2025年沖縄のお墓参り清明祭(シーミー)の進め方は?

2025年も沖縄のお墓参り行事、清明祭の時期がやってきました。古いご先祖様の按司墓(あじばか)がある家では、前半が神御清明祭(カミウシーミー)、後半が清明祭のお墓参りとなります。2025年は4月4日(金)~19日(土)が清明(せいめい)の節気にあたります。
今回は、2025年の清明祭の進め方について解説していきます。
清明祭とは先祖供養の墓前祭
沖縄で行われる清明祭は墓前で行うお祝い行事とされてきました。したがって清明祭はご先祖様とともにお祝いをするのが目的となっています。
本土のお墓参りは「思い立った時にいつでも」お参りできることが風習となっていますが、沖縄では年中行事以外にむやみにお参りしてはならないとされてきました。その理由は「他の霊が羨むため」などと言われますが、実際には遺体を風化させる葬送方法「風葬」の歴史がその背景にあります。
清明祭の進め方は?
◇清明祭の拝み方
沖縄のお墓には左側(向かって右側)に「ヒジャイガミ(左神)」と呼ばれる墓地を守る土地神様がいらっしゃいますので、清明祭に限らず、お墓に着いたら最初にヒジャイガミへ拝んでください。ヒジャイガミへ拝んだ後は墓前での拝みを行います。
<清明祭の進め方>
①ヒジャイガミへ拝む
②墓前へ拝む
清明祭(シーミー)のお供え物に、重箱料理のおかずを補充する「ウチジヘイシ」があるのは、ヒジャイガミへの拝みの後、お皿に数品ずつおかずを取り分け、ヒジャイガミへ供えるためです。それぞれ少し詳しく解説していきましょう。
①ヒジャイガミへ拝む
ヒジャイガミへは重箱料理2重、お酒とヒラウコー(平御香)を供え拝むだけです。ヒジャイガミはご先祖様ではなく「神様」なので、お供え物も神様への税金と言われる、半紙を四つ切りにして作る「シルカビ」を添えましょう。
<ヒジャイガミへの拝み方>
①お供え物を供える
・重箱料理…おかず重1重、もち重1重(合計2重)
・お酒
・シルカビ
・ヒラウコー(平御香)
②重箱料理からおかずを取り出す
・1品目につき1~2個ほど取り出す
・おかずをひっくり返し、重箱の上に乗せる
③家長を中心に、ヒジャイガミへ拝む
・いつもお墓をお守りいただき、ありがとうございます
・これから2025年の清明祭(シーミー)を行います
・どうぞ無事に済ませることができますよう、お見守りください
④シルカビを焚く
・カビバーチでシルカビを焚く
・上から供えていたお酒を掛ける
⑤おかずをお皿に盛りつける
・重箱にのせたおかずをお皿に盛りつけて供える
・重箱の空いた部分に、ウチジヘイシからおかずを補充する
カビバーチには水を張り、悪疫祓いのネギなどを浮かべて準備をし、その上でシルカビを焚いてください。
②墓前へ拝む
墓前でお供え物を供え、拝んだ後、ウチカビを焚いたら一緒に食事(ウサンデー)をいただきます。昨今はさまざまな影響で集まる親族が少ない場合もありますが、その分ウチカビを多く焚く必要はなく、参加した人数分のウチカビを焚けば大丈夫です。
ただ、大きな門中では、家の代表が清明祭に訪れ、家族の代理として家族分のウチカビやヒラウコー(平御香)を供えるしきたりもあります。
<墓前での拝み方>
①お供え物を供える
・重箱料理…おかず重2重、もち重2重(合計4重)
・お酒
・水
・お茶
・供花…左右1対、2束
・果物の盛り合わせ
・お菓子の盛り合わせ
・ウチカビ…家長5枚、その他3枚/1人
②ご先祖様へ拝む
・家長を中心に拝む
・家長のヒラウコー(平御香)…2枚(12本分)
・その他の人…半分(3本分)
③ウチカビを焚く
・家長から順番にウチカビを焚く
・お供え物のおかずを、焚いたウチカビの上に置く
・墓前でご先祖様と一緒に食事をいただく(ウサンデー)
一般的にウチカビは金属ボウルなどのカビバーチ(火鉢)で焚きますが、お墓の右側(向かって左側)にウチカビなどを焚くための「ジングラ(銭蔵)」を設けているお墓もあるかもしれません。ウチカビを焚いた後は、その上に重箱料理からおかずを取り分けて乗せることで、ご先祖様へお供え物が届くと言われています。
まとめ

以上が清明祭の進め方でした。参考になりましたか?繰り返しですが、2025年の清明祭は4月4日(金)~19日(土)です。近年ではコンパクトなお墓や霊園のお墓が増えたことで、家族だけの少人数で行う清明祭も増えています。そんな時は、お供え物も少なめにして、現代の言葉で心を込めて拝みましょう。