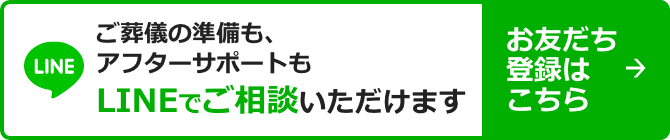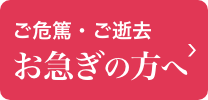お葬式の豆知識
【2025年版】沖縄の七夕とは?8月29日(金)に行われる“ご先祖を迎える日”の意味と過ごし方

七夕と聞くと、多くの人が7月7日に短冊に願いを込めて星に祈るロマンチックな行事を思い浮かべることでしょう。しかし、沖縄における七夕はまったく異なる意味を持つ厳かな“祖先への拝みの日”にあたります。特にお盆直前の重要な行事として、今も多くの家庭で大切にされています。
2025年の沖縄の七夕(旧暦7月7日)は、新暦でいうと8月29日(金)にあたります。この日、沖縄の家庭ではどのように先祖と向き合い、何を行うのでしょうか?本土の七夕とは異なる、その文化的な背景と実際の過ごし方を見ていきましょう。
沖縄の七夕はお盆の準備日
沖縄の七夕は「織姫と彦星が出会う日」というような恋物語ではなく、旧暦のお盆に向けてご先祖様に訪れを知らせる“通告日”としての意味合いを持ちます。
◇七夕の日に行うべきこと
①墓掃除と整備
沖縄では年に数回、暦に従ってお墓を訪れますが、七夕はその中でも重要な1日。特に雑草の繁殖が早い夏場、墓地の整備を怠ると次の訪問時には手がつけられなくなることも。この日は墓石を洗い、周囲の草を刈り、きれいな状態でお盆の準備を整えるのが慣例です。
②お供えと拝み
お墓には果物や菓子、花などを簡易的に供えます。本土のように重箱料理を持参する必要はなく、主な目的は掃除と拝みです。お供えとともに、ご先祖様に「まもなくお盆です。お迎えの準備をしています」と伝えることが七夕の本質となります。
③お線香とシルカビ
沖縄のお墓参りでは、お墓の土地神様である「ヒジャイガミ(左神)」を最初に拝む必要があるので、お線香は多めに準備をしましょう。ヒジャイガミはご先祖様ではなく神様なので、「神様への税金」とされるシルカビ(半紙など)を一緒にお供えすることも忘れないようにしましょう。
④お祈りと感謝
お墓参りの拝みは、祖先の霊に対する感謝の気持ちと家族の繁栄や健康、お盆の訪れをお知らせするなどをグイス(祝詞)を唱えますが、ウチナーグチ(沖縄言葉)でも現代の言葉でも問題ありません。拝む順番は、ヒジャイガミ、墓前、家に帰ってからは仏壇にそれぞれ拝みますが、火の神「ヒヌカン」がいる家庭では、七夕の日であることを朝一番に報告しましょう。
⑤お墓の修理
沖縄では暦や吉凶を大切にしますが、七夕だけは日取りを気にせずに良い日だと認識されています。そのためお墓の修理や引越しをするのに適した日だとされています。また、洗骨という風習があった頃は、旧暦の七夕に洗骨行ったり、墓じまいや仏壇じまい、お墓の引っ越しなども行ったりする日にあてられることが多いです。
お墓の修繕や改葬にも適した日

沖縄では日取りや暦を非常に大切にしますが、七夕の日は「吉日」とされる珍しい日。お墓の修理や改葬(お墓の引越し)を行うには絶好の日とされており、昔ながらの洗骨(遺骨の洗浄)もこの日に合わせて行われることが多かったといいます。
また、仏壇じまいやお墓じまいを行う際にも、七夕の日を選ぶ家庭があります。こうした大きな節目に合わせて行動するのも、沖縄らしい伝統文化の一部です。
| 七夕の日の一連の流れ | |
| [時間帯] | [行うこと] |
| ◆朝 | ヒヌカンに七夕の日であることを報告 |
| ◆午前中 | 家族でお墓へ:掃除・お供え・拝み |
| ◆昼頃 | 仏壇に報告(在宅にて) |
| ◆地域によって | 七夕イベントに参加 |
以上は沖縄の七夕の一日の流れになります。毎年のことですが、家族揃ってご先祖様へのお盆の報告やお墓参りなどをしっかりと行いましょう。
◇地域によっては「七夕まつり」も行われる

基本的にはお墓掃除とご先祖への拝みが中心の沖縄の七夕ですが、地域によってはコミュニティ行事や祭りが開催される場所もあります。
・子ども会によるエイサー演舞
・公民館や広場での地元芸能披露
・簡易な屋台や夜店の出店 など
こうした行事は、地域住民のつながりを再確認する機会として、離島や旧市街では特に大切にされています。
まとめ:七夕は“ご先祖との約束の日”
沖縄の七夕は、本土でよく知られるロマンチックな「星祭り」とは異なり、祖先とのつながりを意識する実践的な1日で、お盆に先立って準備を整え、ご先祖を迎える「入り口の日」として、大切にされてきた文化的行事です。親族が集い、お墓を整え、心を込めて手を合わせることで、家族の絆や命のつながりを再確認する機会になることでしょう。