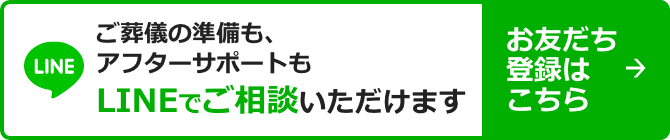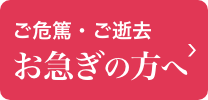お葬式の豆知識
葬儀保険の種類と選び方ガイド|保険金定額型と保険料一定型の違いとは?

近年では、終活の一環として「葬儀保険」に加入する人が増えています。手頃な保険料で葬儀費用を補うことができるため、高齢者を中心に特に関心が高まっていますが、実は葬儀保険にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やメリットが異なっています。
今回は、「保険金定額型」と「保険料一定型」という2つの基本タイプの違いを解説し、どのように選べばよいかのポイントを紹介します。葬儀費用の相場データもあわせて紹介するので、実際の負担に見合う保険選びの参考にしてください。
葬儀保険には2種類ある
葬儀保険は、主に以下の2タイプに分かれます。
・保険金定額型:保険金額が一定で、年齢に応じて保険料が上がるタイプ。葬儀費用をしっかりカバーしたい人におすすめ。
・保険料一定型:保険料が一定で、年齢に応じて保険金額が下がるタイプ。支出を抑えながら備えたい人におすすめ。
それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
保険金定額型とは?
「保険金定額型」は、月々の保険料が更新時の年齢に応じて増加しても保険金額(受け取る額)が一定に保たれるタイプです。年齢が上がるにつれて保険料は高くなりますが、支給される保険金額が変わらないため、将来の葬儀費用を確実にカバーしたい人に向いています。下記はあくまでも一例ですが、50歳・65歳と、更新時に保険料が上がります。
<保険金100万円のタイプの保険料推移の例>
・49歳まで:月々1,200円
・50歳から:月々1,760円
・65歳から:月々2,400円
◇メリット
・加齢後も同じ保険金が支給される安心感
・プランがシンプルで管理しやすい
◇デメリット
・年齢が上がると月々の支払いが負担になる可能性
加齢に伴って支払う保険料が増えても、受け取る保険金は一定なので、保険金がしっかりと必要な人におすすめです。
保険料一定型とは?
「保険料一定型」は、毎月の保険料が一定で、年齢が上がると保険金が減額されるタイプ。経済的な負担を抑えつつ葬儀に備えたい人向きです。こちらも下記はあくまでも一例ですが、年齢と反比例して受け取る保険金が減額します。
<月1,000円の保険料での保険金額推移の例>
・64歳まで:保険金55万円
・65歳から:保険金45万円
・75歳以降:保険金35万円
◇メリット
・ずっと同じ保険料で安心
・家計のコントロールがしやすい
◇デメリット
・加齢とともに保険金が減る
・実際の葬儀費用に届かない可能性も
加齢に伴う経済的な負担を軽減したい人、葬儀費用の一部だけを補填したい人に向いているタイプです。
葬儀費用の相場と保険金額の目安

保険を選ぶには、「どれくらいの費用が必要なのか」を知っておくことが重要です。以下は、2023年時点での主な葬儀形式別の費用相場です。
| <2023年:全国の葬儀形式別の費用相場> ●基本料金+変動費 |
|
| [葬儀形式] | [平均的な費用相場] |
| ①一般葬 | ・約100万円~120万円 |
| ②一日葬 | ・約80万円~100万円 |
| ③火葬式 | ・約20万円~40万円 |
| ④直葬 | ・約20万円~40万円 |
| ⑤家族葬 | ・約30万円~20万円以下 |
たとえば「最低限の形で直葬をしたい」と考えるのであれば、30万~50万円の保険で対応できるかもしれません。一方で、通夜・告別式を含む一般葬を望む場合には、100万円前後の保険を視野に入れましょう。
保険選びで確認したい4つのポイント
① 必要な保険金額を把握する
希望する葬儀形式から逆算して、必要な保険金額を見積もりましょう。
② 現在の家計状況と今後の支出を考慮する
無理のない保険料設定が重要です。年金生活でも継続できる金額に抑えることが肝心です。
③ 既存の保険との重複を避ける
生命保険などに葬儀費用相当の保障が含まれていないか、事前にチェックしておきましょう。
④ 支払いタイミングを確認する
保険金の支給が「迅速に現金で行われる」商品を選ぶことで、葬儀直前の立替えリスクを回避できます。
まとめ

葬儀保険には「保険金定額型」と「保険料一定型」の2つの基本タイプがあり、それぞれのライフスタイルや経済状況に応じた選び方が大切です。
・しっかり備えて安心したい → 保険金定額型
・支出を抑えて柔軟に対応したい → 保険料一定型
どちらの型を選ぶにしても、まずは希望する葬儀形式や費用を明確にすることが、最適なプランを選ぶための第一歩です。将来の安心のために、早めに選択肢を把握し、準備を進めましょう。